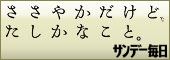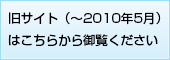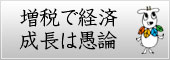ニッポン維新(132)民主主義という幻影―18
 ロッキード事件の3年後にグラマン事件が起きます。これはアメリカの証券取引委員会(SEC)が軍需企業グラマン社を告発したもので、日本に早期警戒機(E2C)を売り込むため、代理店の日商岩井を経由して岸信介、中曽根康弘、福田赳夫、松野頼三氏に賄賂を渡したという事件です。
ロッキード事件の3年後にグラマン事件が起きます。これはアメリカの証券取引委員会(SEC)が軍需企業グラマン社を告発したもので、日本に早期警戒機(E2C)を売り込むため、代理店の日商岩井を経由して岸信介、中曽根康弘、福田赳夫、松野頼三氏に賄賂を渡したという事件です。
ロッキード事件と違って収賄政治家の名前がアメリカから公表されました。しかし東京地検特捜部が逮捕したのは日商岩井の関係者のみで、「巨悪は眠らせない」と大見得を切りながら、「時効と職務権限の壁に阻まれた」事を理由に政治家を事情聴取する事もなく事件は幕引きされました。
ただこの事件は一人のアメリカ人の名前をクローズアップさせました。ニューズウィーク誌で外信部長を務めていたハリー・カーンという人物です。グラマン社の売り込み工作のコンサルタントとして名前が出ました。この人物こそ「戦後の日本を作った男」と言われています。
ニューヨーク在住のジャーナリスト青木富貴子さんが最近出版した「昭和天皇とワシントンを結んだ男」(新潮社)は、占領期にニューズウィーク東京支局長を務めていたコンプトン・パケナムの日記を素材にしたものですが、取材のきっかけはアメリカ人ジャーナリストから「戦後の日本を作ったのはハリー・カーンだ」と聞かされ、ハリー・カーンを調べていくうちに部下であるパケナムの日記にたどり着いたのです。
パケナムの日記によれば、鳩山一郎政権も岸信介政権も誕生の背景にはハリー・カーンらの画策があった事が分かります。特にA級戦犯だった岸信介氏とハリー・カーンの関係は密接です。ハリー・カーンはニューズウィーク誌を辞めた後、中東産油国のコンサルタントになりますが、その頃日本は自国の石炭産業に見切りをつけ、遠い中東の石油に依存するようになります。それもハリー・カーンの影響ではないかと思わせるほど、カーンは日本の政治に介入していました。その存在を初めて国民に知らしめたのがグラマン事件でした。
このようにロッキード事件もグラマン事件も戦後の日米関係の闇の部分を垣間見せ、しかし何も解明されずに終りました。そして世間から「最強の捜査機関」ともてはやされた検察の内部には、事件を解明できなかった事に対する若手の不満が満ちていました。当時東京地検を担当する記者だった私はそうした声を聞いています。
しかしメディアは前総理を逮捕した検察を「巨悪を眠らせない正義の存在」と国民に思い込ませ、国民は「政治とカネ」の問題に憤ります。その国民世論を背景に三木武夫総理は政治資金規正法の改正に乗り出しました。法律の主旨を変更する大改正です。前にも書きましたが、政治資金規正法の「正」の字が「制」でない事に注目して下さい。政治資金規正法の主旨は政治献金を「規制」する事ではなく、政治資金の「透明化」を主眼としたものです。
日本に政治資金規正法が出来たのは1948年ですが、GHQの指導によってアメリカの腐敗防止法をモデルに作られました。アメリカは献金を集める能力こそが政治指導者にふさわしいと考える国ですから、金額を規制してはおりません。従って日本の政治資金規正法も金額を規制する法律ではありませんでした。それがロッキード事件によって金額を規制する法律に変わります。
その結果、政治の世界は浄化されたでしょうか。実態は逆になりました。献金は闇に潜るようになり、裏金がまかり通るようになったのです。事の善し悪しは別にして、それまでの日本では「民主主義のコスト」としての政治献金を大企業の交際費の枠内で認めていました。ところがロッキード事件で丸紅が摘発され、大企業は献金をためらうようになりました。代わって政治献金の主体となったのがベンチャー企業です。
一方で政治資金規正法の改正は検察による政界捜査の可能性を高める筈でした。ところが検察は政界捜査を行なわなくなりました。ロッキード事件の後遺症で検察は動けなくなったと噂されました。その検察が再び政界捜査に乗り出したのはロッキード事件から10年後の事です。東京地検特捜部は撚糸工連事件で与野党議員を一人ずつ起訴しました。ところがこれは民主主義にとって極めて問題の多い事件でした。(続く)