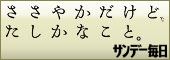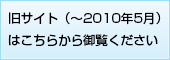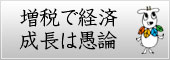ニッポン維新(141)民主主義という幻影―27
 宮本雅史氏の後輩にあたる産経新聞の石塚健司記者が『「特捜」崩壊』(講談社)を出版したのは2009年です。日本で初めての政権交代が実現する直前でした。石塚氏も検察の捜査を20年近く追い続けてきたベテラン司法記者です。「日本最強の捜査機関」を信頼し、「政官財に巣食う病巣にメスを入れる特捜検事の使命感」に共感して取材をしてきました。
宮本雅史氏の後輩にあたる産経新聞の石塚健司記者が『「特捜」崩壊』(講談社)を出版したのは2009年です。日本で初めての政権交代が実現する直前でした。石塚氏も検察の捜査を20年近く追い続けてきたベテラン司法記者です。「日本最強の捜査機関」を信頼し、「政官財に巣食う病巣にメスを入れる特捜検事の使命感」に共感して取材をしてきました。
ところが2008年に友人が特捜部の捜査対象となり、被疑者の立場から検察の捜査を見た事が、本を書く動機となりました。石塚氏はこの本で二つの事件を取り上げ、特捜部の捜査手法の異常さを指摘しています。二つのうち私が興味を持ったのは1998年に摘発された「大蔵省・日銀接待汚職事件」でした。
事件のきっかけは、97年に摘発された総会屋への利益供与事件で、証券会社や銀行を家宅捜索した中から、大蔵官僚を接待していた領収書や伝票が見つかった事だとされています。特捜部は当時37歳の大蔵省課長補佐をターゲットに捜査を始めました。この若手官僚は上司と共に数多くの宴席に出席していました。検察にとって格好のターゲットです。
ところが宴席には東京地検から大蔵省に出向していた検事も同席していました。しかもその検事は大蔵省の出向が終った後も証券会社の接待に応じています。事件化すれば検察の恥部をさらす事になりかねません。普通なら捜査を見送る可能性もありました。しかし特捜部は身内の容疑事実をすべて隠蔽し、「昭電疑獄事件」以来50年ぶりとなる大蔵省キャリア官僚の逮捕に突き進みます。
金融機関が大蔵省の官僚を接待している事実は誰でも知っています。「護送船団方式」と呼ばれ、大蔵省に手取り足取り指導されなければ何も出来ない仕組みがこの国の金融機関にあるからです。総会屋の事件などなくとも摘発しようと思えば出来たはずです。なぜこの時期に、しかも身内の不祥事を隠蔽するリスクを犯しながら強引に摘発に踏み切ったか、私の見方を後述します。
検察捜査のいつものパターンで被疑者を「悪者」に仕立てる情報操作から捜査は始まりました。この時メディアにリークされたのは「ノーパンしゃぶしゃぶ」という特殊な接待です。しゃぶしゃぶを食べる際に若い女性が下着を着けずにサービスする宴会で接待を受けていたと言うのです。これで国民感情に火がつきました。それまで「官僚の中の官僚」と呼ばれ、メディアも批判を控えてきた大蔵省が薄汚い役所と見られ、威信は地に堕ちました。
逮捕された若手官僚は先輩と共に宴席に出ていただけで、見返りに接待相手の便宜を図ったわけではありません。ところが検察は「接待には贈賄の趣旨があった」という金融機関の供述調書を数多く積み上げます。金融機関は「そう言わなければお前も起訴する。言えば起訴しない」と検事に脅されていました。これも検察のいつもの手口です。収賄の認識がない若手官僚は潔白を晴らそうとしますが、そのためには企業側の供述調書の嘘をすべて証明しなければなりません。証明にどれほどの時間がかかるか気が遠くなる話です。弁護士に説得された若手官僚はいわば人身御供となって罪に服しました。
この事件は折からの金融危機と相まって大蔵省批判を強めさせました。大蔵省は財務省と金融庁に分割され、天下り先の多くを法務官僚に奪われました。しかし私がこの事件に興味を抱くのは、この事件の前にアメリカのクリントン大統領が「大蔵省、通産省、東大」を「日本の三悪」と呼んで日本を批判していた事実です。当時のアメリカは大蔵省と通産省、そして官僚主導の日本経済を「アメリカの敵」と見ていました。私にはこの事件がアメリカの意向に沿った捜査に思えるのです。(続く)