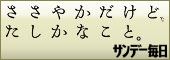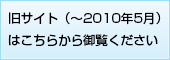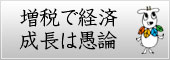ニッポン維新(149)民主主義という幻影―35
 私がロッキード事件の取材で東京地検特捜部を担当する事になった時、先輩記者から「検察は政治的な組織である。悪い人間を捕まえるのではなく、国家の安寧秩序に障害になる人間を捕まえるところだ」と言われました。先輩記者は検察と警察の違いを私にそのように教えました。
私がロッキード事件の取材で東京地検特捜部を担当する事になった時、先輩記者から「検察は政治的な組織である。悪い人間を捕まえるのではなく、国家の安寧秩序に障害になる人間を捕まえるところだ」と言われました。先輩記者は検察と警察の違いを私にそのように教えました。
また「現場の検事に取材すると記者クラブから除名される。その代わり幹部が日に2回会見をしてくれる。そして幹部の自宅への夜回りが重要な取材源だ」と言われました。つまり取材対象は検察幹部に限られ、それ以外の取材は許されないと言うのです。検察は国家の安寧秩序を乱すいわば「国家の敵」を相手にするのだから制約があるのは仕方がないと言う事でした。
私は検察が発表した情報の「ウラ」をどうして取るのかと思いました。捜査を担当する複数の検事から情報を取れば、話の食い違いやニュアンスの違いから、発表された情報と異なる輪郭を掴む事も出来ますが、幹部しか取材できなければ統制された情報しか取れません。我々は検察のコントロールのままになります。
しかも検察の捜査には事件の現場がありません。警察取材では我々も事件の現場に行き、周囲の聞き込みなどを行なって事件の輪郭を掴む事が出来ます。しかし検察は家宅捜索で押収した証拠の分析と取り調べでの被疑者の供述が捜査のポイントです。いずれも我々は立ち会うことが出来ません。従って我々は検察幹部の発表を信ずるしかないのです。
ロッキード事件の夜回り取材で古手の記者が東京地検の検事正にこんな質問をしました。「昔は取調室の前で記者が待ち受けていて、取調室から出てきた検事に直接調べの模様を聞く事が出来たそうじゃないですか。なぜ今は駄目なんですか」。「売春汚職の真相をそろそろ話してくれても良いではありませんか。本当は読売のスクープ通り逮捕状は3本あったのでしょう?」。いずれの質問にも検事正は黙って微笑むだけでした。
当時の検察庁舎には取調室が並ぶフロアーがありましたが、そのフロアーに我々が立ち入る事は厳禁だと先輩記者から言われていました。それを破ると記者クラブ除名になると言われました。しかし古手の記者の話では昔はそこにまで記者が詰め掛けていたようです。それがいつからか禁止となり日に2回の会見だけでメディアは満足するようになっていました。
私はある日思い切って取調室のあるフロアーに行ってみました。エレベーターを降りると無人の廊下があり取調室のドアが並んでいます。廊下の向こうに衛視がいてこちらを睨んでいました。あまりの静けさに面食らい、思いもしないプレッシャーがこみ上げてきました。聖域に踏み込んでしまったという感覚で身動きがとれなくなりました。
売春汚職は売春禁止法の成立を巡り赤線業者が自民党の政治家に贈賄工作をした事件です。読売新聞が国会議員3人を「逮捕」と報じました。しかし検察が逮捕したのは1人だけで、記事を書いた記者は逮捕されなかった国会議員から名誉毀損で訴えられます。記者は裁判で情報源を明かすよう迫られましたが、それを拒否して有罪判決を受けました。記者は有名な特ダネ記者でしたが左遷をされ失意のうちに自殺しました。
夜回り取材で検事正は何も答えませんでしたが、後に伊藤栄樹検事総長が検察内部の情報漏れを特定するためわざとガセネタを流した事を自身の本で明らかにしました。そのガセネタに泳がされて記者は誤報を書かされ、それによって現職の国会議員らは名誉を傷つけられ、そして記者は自殺に追い込まれたのです。「国家の敵」と戦っているという検察の意識が平然とガセネタを流させていました。しかしメディアにはガセネタを見極める術がないのです。
ロッキード事件の2年後に起きたグラマン事件はロッキード事件と全く同じ構図です。アメリカの軍用機売り込み工作で日本の政治家に賄賂が流れました。アメリカの証券取引委員会は収賄政治家として岸信介、福田赳夫、中曽根康弘、松野頼三の名前を明らかにしました。当時の伊藤栄樹刑事局長は国会で「巨悪は眠らせない」と大見得を切りましたが、政治家は誰も逮捕されませんでした。
「時効と職務権限の壁に阻まれた」と検察は言い訳しましたが、メディアにはそれを確かめる術もありません。検察は悪い人間を捕まえるところではなく政治的に動く組織だということを再確認させられました。「国家の敵」と戦っているという検察の意識と自主規制して検察に迎合するメディアの存在が、検察を歪んだ組織に変貌させて行くのです。(続く)