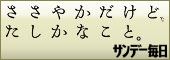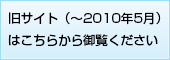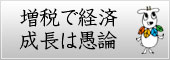ニッポン維新(164)情報支配―14
 司法記者クラブのある日、毎日新聞が現場の検事から聞き出したと思われる特ダネを朝刊の一面で報じました。すると検察幹部のその日の会見は毎日新聞に対する叱責から始まりました。「毎日の記者はいるか。いるなら俺は何もしゃべらん」。幹部はそう言って記者席を睨み付けました。
司法記者クラブのある日、毎日新聞が現場の検事から聞き出したと思われる特ダネを朝刊の一面で報じました。すると検察幹部のその日の会見は毎日新聞に対する叱責から始まりました。「毎日の記者はいるか。いるなら俺は何もしゃべらん」。幹部はそう言って記者席を睨み付けました。
しばらく沈黙が続きます。私は全社の記者が席を蹴って立ち上がると思いました。しかし誰も立ち上がりません。新人記者の自分だけでも抗議をしようかと思った時、「他社の方々に迷惑をかけたくはありません。不本意ではありますが退席します」と毎日の記者が立ち上がり会見室から出ていきました。
記者が出ていくと張りつめていた空気が緩み、いつものように記者会見が始まりました。なぜ記者クラブは結束して毎日の記者を擁護する側に回らないのか。私はいたたまれない気持になりました。しかし新人の私が何か言っても無意味に思え、このグロテスクな状況を胸に焼き付けて忘れないようにしようと思いました。
これが記者クラブの中でも最悪と私が思う司法記者クラブの実態です。しかし司法記者クラブが昔からそうだったかと言えばそうではありません。昔は記者たちが取調室の前で待ち受け、取り調べを終えたばかりの検事に自由に取材をしたようです。それが次第に制約されるようになり、今では記者クラブが進んで自らの手足を縛るようになりました。
その間に一体何があったのでしょうか。一つの事例を元読売新聞記者で作家の本田靖春氏が著書『不当逮捕』に書いています。それは一人の特ダネ記者が検察に逮捕され自殺するまでの実話です。1957年に東京地検が摘発した売春汚職事件で、数々のスクープをものにしてきた読売新聞のスター記者が、政治家3人の名前を挙げて検察が逮捕すると報じました。
ところがその中の2人が名誉棄損で読売新聞を訴えます。すると検察は直ちに記者を逮捕して情報源を明かすよう迫りました。記者は情報源の秘匿を貫きます。結局、検察が逮捕した政治家は記事に書かれた中の1名だけで、記者は名誉棄損で有罪判決を受けました。
読売新聞社も日本新聞協会も当初は記者の釈放を要求して戦う姿勢を見せました。しかし2人の政治家の名誉棄損が認められ記者が有罪になると姿勢は一転します。記者は左遷され記者生命を絶たれました。失意の記者はヒロポン中毒となり自殺します。
後にこの誤報は検察内部の派閥争いに巻き込まれ、敵対する派閥を一掃しようとする謀略の犠牲になった事が分かりました。当時、検察内部には「公安検察」と「特捜検察」の2つの派閥があり、特捜派から捜査情報が漏れていると見た公安派がわざとガセネタを流し、それを記事にした記者を逮捕して情報源を自白させ、特捜派を一掃しようとしたのです。その経緯は伊藤栄樹元検事総長の回想録『秋霜烈日』にも書かれています。
このスター記者の逮捕は「社会部王国」を誇った読売新聞社に打撃を与えました。この時から読売社会部の凋落が始まったと言われています。同じように毎日新聞社を経営危機に追い込んだのも敏腕と言われた政治部記者の逮捕からでした。1972年、沖縄返還交渉に絡む「密約」の存在をスクープした西山太吉記者は、国家公務員法違反の共犯として逮捕され、それが毎日新聞社の凋落の契機になりました。
特捜検察を18年間担当し、検察内部に食い込んだ敏腕として知られる産経新聞の宮本雅史記者も、検察幹部から「検事総長があなたを逮捕しろと言っている。あなたに情報を流した検事の共犯として国家公務員法違反だ。自重した方が良い」と脅された事を著書『歪んだ正義』で明かしています。
つまり記者が官僚機構に食い込んで得た情報が、官僚機構にとって許されない情報であれば、情報を流した官僚と記事を書いた記者はいつでも国家公務員法違反で逮捕できると日本の検察は言っているのです。その脅しに屈したかのようにメディアは自らの手足を縛るようになったのです。(続く)