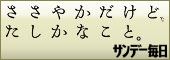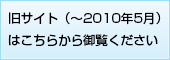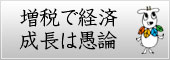ニッポン維新(165)情報支配―15
 記者にとって情報源の秘匿は基本中の基本です。それをしなければ誰も真相を語ってはくれません。売春汚職を取材した読売新聞の記者はその原則を守り通し、そのために有罪判決を受け、記者生命を絶たれて自殺しました。その背後に情報がメディアに漏れることを極度に恐れる官僚権力の強い意志があります。官僚機構には「知らしむべからず」のDNAがしっかりと組み込まれているのです。戦後の民主化政策によって一時は情報を国民に公開する民主主義の意義が唱えられました。しかし時がたつにつれ官僚機構のDNAが再び姿を現してきました。
記者にとって情報源の秘匿は基本中の基本です。それをしなければ誰も真相を語ってはくれません。売春汚職を取材した読売新聞の記者はその原則を守り通し、そのために有罪判決を受け、記者生命を絶たれて自殺しました。その背後に情報がメディアに漏れることを極度に恐れる官僚権力の強い意志があります。官僚機構には「知らしむべからず」のDNAがしっかりと組み込まれているのです。戦後の民主化政策によって一時は情報を国民に公開する民主主義の意義が唱えられました。しかし時がたつにつれ官僚機構のDNAが再び姿を現してきました。
売春汚職事件では情報を漏らす検事をあぶりだすためにわざとガセネタを流し、それを記事にした記者を逮捕して情報源を自白させようとしました。記者が情報源を守り通したため情報を漏らした検事は救われますが、記者は謀略の犠牲となりました。
情報漏えいを許さない官僚機構の姿勢は、事件後の司法記者クラブで徹底されていきます。幹部が記者会見を毎日2回やる代わりに記者が現場の検事に接触する事が禁止されました。幹部が会見で発表する内容は組織として認められた統制情報です。ルールを破ったメディアを記者会見に同席させず、さらに取調室を聖域化して記者の立ち入りを禁じました。
こうした規制にメディアが抵抗できなかったのは、検察が独自に逮捕・起訴できる強大な権限を有している事や、検察の取材には「現場」がないため情報操作しやすい事などが挙げられます。例えば同じ捜査機関でも警察の取材には事件の「現場」があります。メディアは警察の発表だけで記事を書く訳ではなく、「現場」を足で歩き、聞き込みや証拠集めをして記事を書きます。そうした場合には情報統制などできません。
ところが検察の捜査の「現場」は取り調べを行う密室です。取り調べ担当の検事を取材できず、取調室にも近づけなければ、そこでどのような取り調べが行われたのかをメディアは知る術がありません。検察幹部が発表すべきと判断した内容だけがメディアに伝えられ、メディアは検察の描くストーリーに乗せられてしまうのです。
それが検察による大衆操作も可能にします。「検察の捜査はナチスのゲッベルス的手法だ」と私に言った警察幹部がいました。ゲッベルスはナチスの宣伝相ですが、その手法はマスコミを使った大衆操作です。マスコミを動員して大衆に一つのイメージを植え付け、それから政府が動き出せば大衆を熱狂させることが出来るというのです。大衆操作がナチスに強大な権力を与えました。
「検察は動き出す前に必ずマスコミを使って大衆に摘発の対象が悪だというイメージを植え付ける。悪を摘発する検察は常に正義の味方と大衆は思い込む。大衆は裁判をやる前から逮捕された人間を有罪と考え、民意を無視できなくなった裁判官は有罪の判決を出す。これが検察のゲッベルス的手法だ」と警察幹部は言いました。
例えばリクルート事件の江副浩正氏や福島県汚職事件の佐藤栄佐久氏は悪のイメージを報道され続けた後に検察に逮捕されました。しかし江副氏の著作『リクルート事件 江副浩正の真実』や佐藤氏の『知事抹殺』などを読むと、それが意図的に作り出されたイメージである事が分かります。
外務省の「密約」を暴いた毎日新聞の西山太吉記者は、情報を外務省の女性事務官から入手しますが、二人には男女関係がありました。すると検察は「情を通じて」情報を入手したと発表し、「情を通じた」部分を強調しました。その結果、大衆は「密約」を暴いた社会的意義よりも、取材のいかがわしさに目が向き、毎日新聞は不買運動にさらされました。こうして官僚機構の思惑通り「密約」の存在は封じ込められていったのです。
事件後、外務省は記者が記者クラブ以外の部屋に立ち入ることを禁じました。外務省の各部屋には極秘文書があるというのが理由です。西山事件を口実にした取材制限が始まりました。記者が官僚に取材で会いに行けるのは夕方の1,2時間に限られ、そのため外務省記者クラブの記者たちは昼間は新聞の切り抜きに精を出すだけでした。
取材制限をする一方で外務官僚たちは「マスコミの報道はピントが外れている」と嘆いていました。外交には秘密が付き物ですから、情報をすべてあからさまにできない事情は分かります。しかし取材制限をすればするほど、外交の現場と国民の認識はずれていき、国家としては困ることが起きるのではないかと私は思いました。私が担当した頃の外務省記者クラブには10年以上も前に起きた西山事件の影がまだ色濃く残っていたのです。(続く)